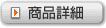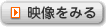“オトナノオンナノコ”。明らかに矛盾したこの言葉。平たく言うと「女はいくつになっても(たとえ30過ぎても)女の子なんだもんっ」って感じなんだろうが、本作はそんな生ぬるい話ではない…。バリバリ働く独身キャリアウーマンのチアキと、キッチンドランカー気味の子持ち専業主婦マサミ。互いを「親友」と呼び合って憚らない2人の、一見真逆の道をゆく人生。はたから見れば、そこそこ幸せに見える彼女たちの人生も、蓋を開ければ不満だらけ。ないものねだりで、互いを強烈にうらやましがりながらも、実ぱ「孤独」というキーワードでしっかりつながれている。そんな微妙なお年頃=29歳の女たちの幸せ探しは、残念ながら、男性諸氏が期待するような美しい旅路ではないかもしれない。彼女たちのバッドトリップはひたすらに貪欲で、あまりに赤裸裸で…そしてかなり、愛おしい。
原作は、せっかく入った大学をわずか3日で中退し、89年「ガロ」より鮮烈にデビューした人気漫画家・安彦麻理絵。当時から一貫して、女性のリアルな生態を真正面から描き続ける彼女だが、そのホップな画風と、まるで小説を読んでいるようなディープな言葉選びは圧巻。当然ながら、熱狂的な女性ファンが多い。
そんな“女度”120%の原作を見事に料理してみせたのが。『パビリオン山楸魚』(06)で日本映画界に衝撃を与えた冨永昌敬監督。30歳を過ぎたばかりの新鋭ながら、『ドルメン』(99)が、2000年ドイツのオーバーハウゼン国際短編映画祭で審査員奨励賞を受賞、2002年には『VICUNAS/ピクーニャ』(02)が水戸短編映像祭でグランプリを受賞するなど、その才能は早くから多くの映画人に認知されていた。「映画は虚構だ!」と潔く振り切らんばかりの(!?)大胆な作風に、やはり熱狂的信者多数。
そんな2人に同じ匂いを感じて…かどうかは不明だが、プロデューサーが本作の企画を冨永監督に持ちかけたところ、実は安彦と冨永は友人同士という事実が発覚!今回の異色コラボが実現した。原作のいい意味での女のいやらしさを残しつつも、ヨーロッパ映画のような洗練されたシークエンス、チアキとマサミのココロの闇を象徴するかのような独特のナレーション、そしてクスクス笑い必至のユーモアセンスなど、随所に冨永カラーが散りばめられているのが秀逸だ。
キャストも映画ならではの個性的かつ豪華な面々。主人公・大久保チアキを演じるエリカ(『ワンダフルライフ』(99)『誰がために』(05))のゴージャスでタフな存在感、もう1人のヒロイン・伊原マサミに扮した桃生亜希子(『Stereo Future』(00)『バウムクーヘンj(06))のガーリーさの中に生々しさを秘めた魅力。リアルな“オトナノオンナノコ”を体現するべく、ハードなシーンにも体当たりしている映画女優2人の熱演は必見だ。そんな彼女たちを支える(翻弄する?)共演陣に、水橋研二、斉藤陽一郎、杉山彦々、高野八誠、河合美智子、津田寛治など日本映画界を牽引する実力派が顔を揃えている。 音楽は、今回、監督たっての希望により渡邊琢磨(COMBOPIANO)が全曲を書下ろしで作曲、またさらに渡邊琢磨、鈴木正人、内田也哉子からなるユニットsighboatが妖しいムード満点の主題歌をつくりあげた。
1979年沖縄県生まれ。 1995年、神山征二郎監督の『ひめゆりの塔』でデビュー。是枝裕和監督『ワンダフルライフ』で主演をつとめ、以降、黒木和雄監督『美しい夏キリシマ』、日向寺太郎監督『誰がために』、青山真治監督『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』、などの作品で印象的な役を演じ、映画女優として活躍する。本年『アコークロー』、本作と立て続けに公開。来年にはアメリカ映画『レイ、最初の呼吸』の公開が控える。
1976年神奈川県生まれ。 1998年、中野裕之監督『SFサムライ・フィクション』でデビュー。以後『Stereo Future ステレオ・フューチャー』、伊勢谷友介監督『カクト』、ソフィア・アコッポラ監督『ロストイントランスレーション』、柿本監督最新作『バームクーヘン』など多数の映画に出演。またCMr日産〜MARCH〜」「花王〜スタイルフィット〜」などでも活躍中。9月29日より、柿本監督最新作『バームクーヘン』が公開される。
1975年東京都生まれ。塩田明彦『月光の囁き』の主演のほか、細野辰輿監督『竜二〜Forever』や行定勲監督『ロックンロールミシン』、石井克人監督『茶の昧』、奥原浩志監督 『青い車』、大崎章監督『キャッチボール屋』など数多くの映画に出演。
1970年北海道生まれ。1996年、青山真治監督の『Helpless』で映画初出演以降、『チンピラ』、『WiLd LIFe』、『冷たい血』、『シェイディー・グローヴ』、『ユリイカ』、『こおろぎ』と、青山作品には欠かせない存在となる。
1978年干葉県生まれ。映画を中心に多数の作品で活躍中。主な作品に金田龍監督『ブギーポップは笑わない』、三池崇史監督『荒ぶる魂たち』・『IZO』、宮坂武志監督『新・影の軍団』、伊勢谷友介監督『カクト』、長石多可男監督『仮面ライダー-THE FIRST-』。
1976年静岡県生まれ。冨永監督作品の常連にして親友、『亀虫』で主役を演じるほか、『VICUNAS/ビクーニャ』、『シャーリー・テンプル・シャボン・パートI&II』、『パビリオン山楸魚』など、ほぼ全ての冨永昌敬監督作品に出演。
1968年神奈川県生まれ。相米慎二監督『ションベンライダー』で主役デビュー。その後も澤井信‐郎監督『恋人たちの時刻』、中田秀夫監督『ガラスの脳』、君塚良一監督『MAKOTO』、大森一樹監督『悲しき天使』に出演。また96年NHK連続テレビ小説「ふたりっ子」で演歌歌手・オーロラ輝子としても人気を博した。
1965年福井県生まれ。北野武監督『ソナチネ』でスクリーンデビュー。その後も映画、テレビにと多数の作品に出演。主な作品に森田芳光監督『模倣犯』、瀧本智行監督『樹の海』、田崎竜太監督『小さき勇者たち〜ガメラ〜』、山口雄大監督『漫★画太郎SHOWババアソーン(他)』、冨永監督作品では『パビリオン山楸魚』に出演。
まず、原作ありきということが今回初めてだと思うのですが、これまでとどこか心構えが変わったところはありますか?
あるんでしょうね。それは原作の映画化ということよりも、今回は作者との関係というか、安彦麻理絵さんが古くからの友達だっていうことが影響してますね。というのも、原作のモデルになった出来事や人物を多少なりとも知ってるつもりですから。それは漫画や小説を映画化するという意味ではフライングだと思うんですよ。だから、事実として漫画を映画化しましたけど、そういう後味がほとんどないというか、作ってくうちに自分のことになってるというか、自分の好きな友達やその家族が出てくる物語ですから、あんまりおかしなことをせずに大事にしようとしたんじゃないですかね。自分のオリジナルの物語だったら、語弊がありますけど、ある意味いい加減にできるんですよ。そうしなかったことが今回大きいなと。『パビリオン山椒魚』も『亀虫』も『シャーリー・テンプル・ジャポン』もそうですけど、自分のオリジナルではありながら、脚本にあまり頓着しないことをあらかじめ決めてるんですね。自分が用意したものを惜しみなく自分で覆すことで作品自体を更新する。コロコロ変わるってことです(笑)。そうすると、最後の最後までどんな映画になるかわかんないわけですよ。いい加減とも適当とも思いつきとも呼べますけど、そういうのを作風として是認してたところがあった。でも今回は、漫画を映画らしく翻案することに注意を注ぐあまり、普段の手癖が出なかった。これはいいことだと思ってます。
もちろん翻案はされていますが、ほとんど原作のままに映画を撮られてますよね。それは原作の方を客観的に見ていると言ってもいいのかもしれないですけど。それは言い方をかえると、ある程度批評もしてるんでしょうね。
チラシに「女の幸せって何スか?」みたいなことが書いてあるけど、そういうことが原作の段階から大筋で問われてるという判断の元で、骨組みを立て直してったというか。たとえば小説や漫画を脚色するときには、どこかしら抜いちゃう部分もあるわけじゃないですか。この部分は漫画では面白いかもしれないけど映画には向かない、みたいなことを僕自身の責任でおこなう。これは原作を対象化する作業ですよ。もう漫画じゃなくなる。漫画で面白かったところでも、これは安彦さんの絵だから面白いんだと思っちゃったらね、どう撮ったらいいんだろうと悩むわけですよ。この通りできるわけがない(笑)。(漫画の「貞子」調の絵を指差しながら)たとえばこれはできないでしょ?これは特撮になるとか、そもそも「リング」のパロディになってしまうとか(笑)。そういうところを抜いてったんです。
そういう部分も含めて、この原作はもっとコメディのようにしようとすればできるわけじやないですか。でもこれってかなりやさしい終わり方ですよね。
何言ってんすか、原作だって最後はやさしいじゃないですか(笑)。コメディにしなかったのだって当然といえば当然なんです。原作の笑いのありようは安彦麻理絵の笑いですから、それを僕がやって再現できるものではないので。原作の不気味な笑いの要素を敬遠したらこうなった、ということです。はじめはね、女の人の話だからな一、なんて思ってたんですよ。これまで安彦さんの漫画を映画にしたいって一度も思わなかったのも、やっぱり女性の物語だから俺には撮る資格がないのだと。でも実際やることになって読んでみると、これ男でもあるよなー、って思えるところがいくつもあって、そういうところほど大事にしたとは思います。男の自分から見てもその気持ちに立つことができたというか、所詮人間であることに変わりなかったという。だから、それほど強く女の子の映画を撮ったっていう意識はないですね。
原作はもっとマサミとチアキってパラレルに描かれています。でも映画だとふたりが同じものを共有している、入れ替わる映画ですよね。分身というか、極端な話を言うとひとりの主人公の話をふたりで撮っているようにも感じます。
それは思いましたね。時間をずらせばそうなってるんじゃないかなっていうのはありますよ。チアキのひょっとしたら3年後くらいがマサミの置かれている状況なんじゃないかなって。
しかし幸福感に溢れた映画ですよね。
凄い感想だな(笑)。まあ、おめでたシーンで終わりますから。でもねえ、これひょっとしたらですけど、最終的にチアキは結婚することになってますけど、あの最後のシーンに淳一いないじゃないですか。あれ、もしかしたら別れているかもしれないですよ。最後に「おめでた=幸せ」ってなってますけど、わかんないですよね。子供ができたって意味では幸せかもしれないけど、ダンナがいないかもしれないし。あー、いらんこと言っちゃった(笑)。
一方で脚本が佐藤有記さんと共同じやないですか。そこは女の人の話を撮るということに関係あるわけですよね。
それはね、女の映画だから女の脚本家というのは方便ですよ。単に自分ひとりで脚本を書くのがいやになったんです。「VICUNAS」とか「パビリオン山椒魚」のときには、どうしても話が誇大妄想的にどんどん広がってって収拾つかなくなったんですけど、このままでは撮れないっていうことでどんどんコンパクトにしていったら、最初に思ってたものと全然違う脚本ができたんですね。そのときはそれでいいと思ってやってたんですけど。完成後、第一稿を見つけて読んでみると、何だこれはって思うわけです(笑)。面白くともなんともないことをめちゃくちゃ書いてる一方で、めちゃくちゃ面白いことも書いてるんだけど、撮影稿であっさり切ってる。俺ものすごく遠回りしてあれを撮ったんだなと。遠回りって言うかわかんないけど。いや、遠回りだな、あれは(笑)。その効率の悪さがいやんなったんですよね。前々から俺は、大事なことと余計なことを判別する能力が人格的に欠落してるんじゃないか、と思ってるんですよ(笑)。映画を撮るための職能としての判断力には自信あるんですけどね。状況対応型っていうか、インプロヴァイザーっていうかね、まあジャズファンってこともあるし(笑)、つまり譜面どおりに演奏できない。作家としての自分と監督としての自分とが没交渉なんですね。それは三年ほど前に梅本洋一さんにも指摘していただいてて、「冨永君そういうの抜けてるよね」って。これはいい意味で言ってくれたんだけど、そんなことをいい意味で言われてる俺もどうかと思うんです(笑)。だからこれはずっと課題としてあったわけです。自分が作るものには、たとえばシーンや台詞の繋がりに因果関係がないとか、気が散りやすいんですね。
それは芯のある一本の物語が見えづらくなっているということですよね。
うん、そうですよ。要はノイズに弱いんですよ、俺は。ついついノイズに耳を貸してしまうんです。そうすると物語が霞んでしまう。そのくらいのことはね、自分でわかってますよ(笑)。でも、それはいずれ克服できるだろうと思ってたんだけど、「パビリオン山椒魚」を撮った時点でとうとうできなかったわけですよね。そうするとどんどん意地になってくわけですよ。何が何でもちゃんとやるんだと(笑)。次はちゃんと大人の対応をしてやろうと、自分に対して大人の対応をしようと。考えてる自分に対して書いてる自分がどうすれば大人の対応できるのかと思ったら、ひとりで書くのをやめればいいという結論が出た。こうね、脚本があってどういうふうな作品になってるか頭の中でシミュレートして、それをちゃんと貫徹するというのはやっぱり意志だと思うんですよ。自分はその意志が弱い監督なんです。絶えざる自己批判の結果そこにたどり着いたわけです(笑)。「お前あんなに言ってたのに現場行ったら忘れてるじゃねえかよ」ってすごく言われるんですよ。「あんなに要る要る言うから用意したのに撮ってないじゃん」とか(笑)。忘れてるくらいだから。そういう意味では、今回は最初から完成まで通して、ある程度ちゃんとできたと思ってます。それまでは、「あ、あれ撮りこぼしちゃったー」って思っても何とかなっていたというか、何とかしてたんですよね。でも、その意志の弱さを何かで補うという方法、後手後手に回らざる得ない性格も含めて作風だと思われてたんじゃないかと。それがいやなわけですよ。
このあとこう行きたいっていうのはありますか、今後の展望ですけども。
今後の展望なんてものは常におんなじですよ。もうね、自分が好きな映画に一歩でも近づくこと以外に展望も糞もないです。思いっきり具体的に言いますけど、アラン・J・パクラみたいなサスペンスを撮りたいですね。そのためには撮影所時代のテクニックが必要なんですけどね。だって俺、基礎がないから、何年かかるかわかんない。そんなにカルトでもないのにカルトって言われてるのが悲しいんですよ。元来そっち指向じゃないから(笑)。自分が撮りたい映画と自分に撮れる映画とのあいだに大きな隔たりがあるんです。何だかんだ言っても、撮れるものを撮ってきましたからね。でもこの頃、ようやく映画の作り方がわかってきたって言うことはできると思うんですよ。こんなに自己批判する映画監督って少ないと思うんだけど(笑)。でも正直言ってそういう感じはしますよ。だからそういう意味で今回は原作っていうものがあって、脚本家と一緒に書いたって言うのがあって、そういう下地ができてたわけだし、この一本前に「パビリオン山椒魚」っていう長編を一本撮ってたからできたっていうのがあるわけですね。あ、余談ですけど、「シャーリー・テンプル・ジャポン」(http://blog.livedoor・jp/shiriey666/)という連作映画の続きを作ってます。いま撮ってるのが「パート3」で、1年後には「パート7」まで完成してるはずです。これに関しては、自分が好きな映画から一歩でも遠ざかること以外に展望も糞もないです(笑)。